
雪が解けない。家の前の大雪だるまはまだ立っている。それもそのはず、練馬では最低気温のマイナスがきょうで10日もつづいている。いかに例年より寒いかということだ。温室内に入れたフクベリー苗は新芽が伸びている。昨日種まきした育苗床のポットの地温は25℃条件が維持できている。(T)

車庫上の水道管破裂は2箇所あり、きょう修復した。すでに24日にレタス、セロリ、パセリはまいたが、今年は少し早めに2回目の種まきをした。ナス科とアブラナ科をポットまきした。今年もキッチンマットヒーターでいくが、70Wだし、例年にない寒さなので地温確保のためホットキャップを被せて保温した。
YouTubeに車庫上園芸180130春野菜の種まきをアップした。(T)

遠い農園にはまだ残雪がある。波板畝の小松菜跡にホウレンソウ(ソロモン)をまいた。マノアの苗を運び、雨よけハウスの中央畝に植えた。ソラマメが元気。正月にカニ殼を酢に浸けて抽出したキチン質酢をはじめて100倍に薄めてニンニクとタマネギに散水した。これから何回か散水して放線菌を増やし、酵素を生産してもらい、さび病をやっつける計画。練馬大根、長悦葱、輝、娃々菜を収穫した。ハイブッシュの剪定をはじめた。
YouTubeに菜園だより180129マノア・キチン質・剪定をアップした。(T)

ファミリー農園の雪はまだ残っている。通路は雪と泥でぐちゃぐちゃ。当分泥濘状態がつづくだろう。カリフローレは葉っぱを被せておいたが寒さで白から飴色がかってきたので収穫した。ほかにホウレンソウ(ソロモン)チンゲンサイ(シャオパオ)を収穫した。秋にファミリー農園で収穫した姫とうがんを保存していたのから種を採種した。表皮にブルームが出ていたので完熟だけあり、充実した種が入っていた。天日干しするには日差しが弱いのでいつものようにテレビの上で乾かした。テレビのバックライトがLEDでない旧型なので適度な熱がありこんな時役に立つ。
YouTubeにファミリー農園180128収穫・トウガン採種をアップした。(T)

昼過ぎ、玄関を出ると車庫上から水が、派手な雪解けだなと思ったのもつかの間、水道管が凍結していたのが溶け出したのだった。すぐに元栓を閉め、車庫上に導いている管に元栓をつけていなかったので急遽取り付けた。いままで設置後17年間破裂したことがなかったので油断した。今後は危ないときは元栓を閉めて水抜きすればOK。明日にでも破裂箇所を修復する。きのう作ったシジュウカラの巣箱を古く朽ちたものと交換した。道端の雪だるまは通りすがりの子供達に蹴られながらもまだかろうじて原型をとどめている。(T)

今朝も練馬はマイナス6.1℃と冷え込んだ。遠い農園の雨よけの最低気温はマイナス8.5℃だった。ハウス内も日が照らないと気温は8℃と低い。プランターに菜っ葉を12月まきで車庫上温室で先日収穫したが、その菜っ葉を間引いたとき、ポット育苗していたのを持って行き、物置ハウスと雨よけハウスに植えた。日が照るのを待っている間、なかなか溶けない雪を軽トラが通れるように入り口からのアプローチ部分約40m除雪した。車庫上のシジュウカラの巣箱が古く朽ちてきたので新箱を作った。標準箱に比べるとスリム型だ。結局、日が照ることはなかったので、苗を植えた。西武池袋線が事故で止まっている情報が入っていたので、八高線で拝島経由で帰宅した。(T)

今朝は練馬の気温がマイナス7℃と近年にない厳しい冷え込みで水道が凍っていた。NGAは、午前中座学。午後はトンネルの雪除去から始まり、消毒済み培土を取り出し、ポットにセロリ、パセリ、マノアをまいた。メインはシジュウカラの巣箱作り。杉板でシジュウカラの標準巣箱を8個作った。千歳門圃場のケヤキの木を中心に設置した。今までに無い木工実習にみなさん楽しそうだった。今春シジュウカラが営巣すれば子育て中は特に大量の害虫駆除になる。(T)

近いのに積雪後の作業が後回しになったファミリー農園へ行った。農園の雪にはまだ一人の足跡しかついていなかった。トンネルが潰れているのにみなさんごゆっくりのようだ。3本の小トンネルは案の定ぺしゃんこ。トンネルの上の雪をどかして、すぐに復旧させた。黒キャベツのカーボロネロが倒れずに立っていた。車庫上温室で今シーズン最初の種まきをした。パセリ、セロリ、レタス類。(T)

きのうの雪は23cm積もった。階下の黒ラブが雪にはしゃいだ。夜途中でやめた家の前の道路の雪かきを終わらせた。雪は大だるまになった。車庫上の百葉箱には雪がこんもり、フクベリーの苗もひとかたまりの雪の中。昼過ぎに遠い農園へ行った。4年前の教訓からハウスの雪害対策は万全にしたので被害なし。防虫網トンネル、古いポリを張ったトンネルは雪が落ちずに潰されたので雪をどかして復活させた。移動式小トンネルは雪が落ちなくても耐えて潰れないほど丈夫だとわかった。興味深いのはタマネギにかけた新品のポリは雪が滑り落ちて無害だった。タケノコハクサイ(チヒリ70)練馬大根を収穫した。
YouTubeに菜園だより180123雪の翌日をアップした。(T)

予報通り雪は午後から本降りになった。落葉のティフブルーにも、遠くのモチノキにも、まだ落葉しないフクベリーの原木にもどんどん積もり、太さ3ミリ以下のエスター線には直径数cmにまとわりつく湿った雪。明日まで何cm積もるのか?(T)

明日の雪予報が本格的・現実的になってきたので、急遽NGA圃場へ向かった。雨よけハウスはすでにつっかい棒で降雪対策はしている。トンネルも保温性のユーラックはそのままにして、防虫網トンネルは雪で潰されないように剥がした。一番潰されたくない大トンネル3つはすべて天井の防虫網をはずした。これで雪対策は一安心。からぶりになっても後悔するよりいい。
今晩の食卓の野菜、台湾小白菜の卵とじ、黄ごころ75のおひたし、サラダはオリンピアレタスとモモちゃんとカリフローレ、ぬか漬けのザーサイと練馬大根の沢庵がおいしい。台湾小白菜はシャキシャキ感があっておいしい。(T)

12月10日まきのプランターの菜っ葉を収穫した。冬でも温室なら1ヶ月ちょっとで収穫になる。途中12月下旬に間引いたのをポットに植えていたのが時間差で苗になっており、収穫後の同じプランターに再移植した。あと2週間もすれば収穫になるので種をまくよりずっと早い。紅ほっぺとモモちゃんも収穫した。晩のおかずにはモモちゃん・カリフローレ・安藤早生のサラダも加わった。安藤早生は柔らかく生でも美味しく食べられる。
YouTubeに車庫上園芸180120菜っ葉など収穫をアップした。(T)

来週、農大でシジュウカラの巣箱作りをしようと思い、その前に予行演習をした。遥か昔に作ったシジュウカラ専用の標準型の箱。15cm幅の杉板128cmで1箱できる。釘ではなく木ねじで組み立てた。シジュウカラ専用にするには出入り口の穴の直径を27ミリにすることなのだが、糸鋸は面倒なので奮発して27ミリのドリルビットを買ってしまった。なんと一瞬できれいな穴が開いた。来週は各班ごとに巣箱を作り、圃場内の邪魔者扱いされているケヤキの木に取り付ける予定。運が良ければこの春からシジュウカラが営巣し、子育てをすれば害虫駆除には大きな効果があるという話にしたい。練馬大根を持ち帰り、2回目のぬか漬けを仕込んだ。1回目が乾きすぎたので、少し早めに感想を打ち切った。(T)

NGAは、午前中から圃場へ、ジャガイモの畝を作るので、まだ収穫が終わっていない芽キャベツを移植した。食の会調理が同時進行。Facebookで知った重曹希釈液でアブラムシ退治を雨よけハウス内で実践。かまど炊きが進む。フクダ流は耕耘機は使用しないのだが、生徒さんの希望があったのでジャガイモ畝の腐葉土撒布、残渣すき込み、ボカシ撒布で耕耘機を入れた。ジャガイモ畝は幅120cm2本で黒マルチを張った。お昼には豚汁が出来上がり、お餅も入っておいしくいただいた。午後、温室で余っていた自家採種のブロッコリー種子を育苗箱にまいて木枠をかぶせ、再びスプラウト栽培。落ち葉積み込みは草花コースと混成で和気あいあいで進んだ。(T)

きょうはまだ雨の予報だったが、来週寒気が来て、南岸低気圧が来ると雪になるので、その前に守るーむを片付けた。上が平らなので雪には必ず潰される。昨年の秋の日照不足で年内の収穫が出来なかったカリフローレがやっと取れた。今シーズンの秋冬野菜の遅れは散々だ。自然には負ける。
YouTubeにファミリー農園180117片付け・カリフローレをアップした。(T)
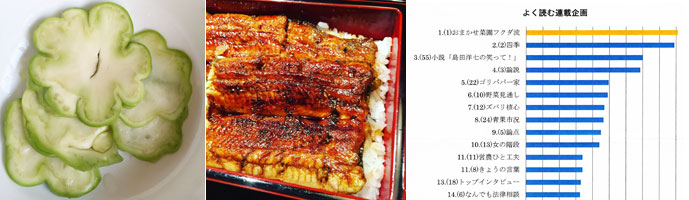
きのうぬか床に漬けたザーサイは浅漬けとはまた違ったぬか漬け独特の風味で美味しく食べられた。
昼は日本農業新聞のお招きで銀座でうなぎの会。おいしくいただいた。今年も読者アンケートでは「おまかせ菜園フクダ流」が前年につづき1位だったそうだ。連載7年目に突入決定。(T)

午前中は雲が多かったが、午後は晴れた。農園には氷が張っていたが、井戸水は13.1℃で温かい。ファミリー農園用のボカシを仕込んだ。プラ舟を池にした。毎年3月にガマがメダカ池に産卵するのでそうさせないように区別することにした。昨年の自家採種のザーサイを収穫した。交雑株はないようだ。フクベリーの誘引ジョイントをつづけた。帰宅後ザーサイを浅漬けの素と練馬大根のぬか床に漬け込んだ。
YouTubeに菜園だより180115ボカシ・ザーサイ・誘引をアップした。(T)

正月にカニ殼にお酢を入れてキチン質を抽出していたのからお酢を抜き取った。クリーム色に濁っている。キチン質が溶け出しているのだろう。カニ殼は捨てずに鉢植えやブルーベリーの根元に置いた。残ったキチン質で何かいいことがあるかも。車庫上のブルーベリーの剪定をした。特に強剪定をするわけでもなく元気な若いを残すようにした。 (T)

外は厳寒期で寒いが車庫上温室内では、12月10日プランターまきの台湾小白菜やコマツナが日に日に成長しているのがわかる。そろそろ収穫期が近付いてきた。ミニレタスマノアはアブラナ科よりは生育は遅いが順調に育っている。相変わらず2年目のミニトマトのモモちゃんがとれつづけている。森の苺も少しずつとれるので、冷凍庫に貯めている。ある程度まとまったらジャムにする。美味しいジャムになる。 (T)

雨よけのトマトの影に植えていた練馬大根が生育遅れだったのだが、いまごろとれたので2回目の沢庵漬けのために寒いので物置ハウスに干した。ブルーベリーの採穂をした。板枠栽培の長悦葱を収穫した。ロケットストーブがまた壊れた。耐火煙突でも使いすぎなのか、高熱で煙突が溶けた。2度あることは3度あると思うと、もう3度目は煙突管式では作りたくない。耐火煉瓦で作ってみるかと思っている。(T)

年明け初のNGA、午前中は野菜品種をテーマにした座学で午後は圃場で実習。ザーサイ収穫。雨よけハウスにマノア、春のセンバツ、台湾小白菜を定植。ダイコン間引き。菜っ葉収穫。カリフローレ、ブロッコリーの残りも収穫。ホウレンソウ初収穫。ザーサイのこぶをスライスして沢庵漬けの糠床へ浸け込んだ。来週食べる。練馬大根の沢庵漬けの試食をした。上出来の美味しさだった。来週は食の会を予定しているのでかまど用の薪割りをした。落ち葉の積み込みをした。(T)

きょうはあすのNGAの座学を新規テーマにしたため、パワポ準備が終わらず、遠い農園には行かなかった。温室内に入るとぽかぽかで、またミニトマトモモちゃんが熟していた。プランター栽培のコマツナもまた大きくなった。パンジーが色とりどりかわいく咲いている。練馬大根の沢庵漬けを少しずつ美味しく食べているが、匂いが強烈なので漬物容器は家の中でなく外に置いて、食べる分だけ取ってくるようにしている。(T)

NGAに下見に行った。練馬大根の沢庵漬けの重しを取り出した。ホウレンソウ(ソロモン)ができている。長悦葱の苗が少しずつ伸びていた。カリフローレに霜よけにかぶせていた葉っぱが外れていたのでまたかけた。ジェットドームもまだ残っている。菜っ葉畝に混植のコーラルリーフプルーム、シャオパオ、三河島菜、ルッコラ、壬生菜などがとりごろ。雨よけハウスのザーサイの根元には大きなコブができていた。造園コースが臨時作業に励んでいた。(T)

どんより曇った成人の日。遠い農園の外トンネルの菜っ葉を収穫した。練馬大根も収穫。ブドウの剪定をした。剪定枝はすぐにチップにした。タマネギに草が生えたので草取りをした。以前は草を生やして寒さよけにしていたが、今年はポリトンネルをかけているので、草を取り、液肥と天恵緑汁とお酢を薄めて散水した。お酢で根張りをよくして冬を乗り切る。今のところ欠株はない。
YouTubeに菜園だより180108ブドウ剪定をアップした。(T)

晴れて風がない分暖かく感じた。家にいるばかりではと近所を散歩した。近くの練馬区立中村かしわ公園にはそのシンボルである柏の木が植えてある。まだ落葉しない。枯葉は芽吹きの頃まで樹上についたままだ。我が家のクヌギも落葉していない。同じだ。温室のパセリが大きくなり葉かき収穫をはじめた。これから初夏にとう立ちするまで収穫がつづく。たくさん取れた時は冷凍保存ができる。来月の野菜の育苗開始を前に、市販の激安培養土から5ミリ目のふるいで大きな塊を取り除いた。(T)

再び快晴の良い天気になった。太陽の光があると昼間の温室内は常夏状態になる。相変わらずミニトマト(モモちゃん)の収穫が続く。肩はり果が標準の紅ほっぺにもほっそりした果実もある。プランター栽培の菜っ葉類が生育旺盛になってきた。安藤早生は間引かなかったので競い合って伸びている。順々に間引き収穫でいけそうだ。間引いたコマツナ(春のセンバツ)台湾小白菜、マノアはがっちり育っている。(T)

きょうは雲が厚く日照がなかったので昼間の気温が上がらず寒かった。ファミリー農園のダイコン(若誉)カブ(飛騨紅丸蕪)キャベツ(輝)を収穫した。(T)

年明け最初の遠い農園へ、その前に高麗神社にお参りをしてから農園へ行った。きょうも北風が強かった。ラビットアイの葉もすっかり散ってしまった。雨よけハウス内のトンネルでコマツナ(安藤早生)三河島菜を収穫した。物置ハウスの間引き移植のチンゲンサイ(シャオパオ)も収穫した。ダイコン(春神楽、天宝)をカイワレが畝に直角のもの1本を残して間引いた。(T)

温室のイチゴ(紅ほっぺ)を口に頬張り、孫たちが帰った。いつもながら急に静かになる。外は北風がかなり強く吹いていた。散歩がてらファミリー農園に立ち寄ると、やっとカリフローレの花蕾が直径15cmほどになっていた。今年はとくに生育が遅い。(T)

昨夜は孫たちの好きなカニ鍋だった。今年はカニ殼を捨てずに利用する。カニ殼にはキチン質があり、水溶性ではないがお酢には溶ける。お酢を入れるとすぐに発泡が始まる。発泡が終わるまで1週間から10日でキチン質が抽出される。その上澄みを水で100倍に薄めて散布するとキチン質を餌とする放線菌が急増し、キチン質を分解するキチナーゼという酵素を出す、ネギ類に出るさび病菌の細胞壁もキチン質なのでキチナーゼに分解され死んでしまうという。(「やさい畑」の記事より)おとどしニンニクがさび病で全滅したことがあった。今年はさび病対策にはカニ殼酢酸でいく。(T)

きのうの厚い雲は去って朝から良い天気になった。風もなく昼間はきのうとは違いかなり暖かく感じた。ゆっくり起きてみんなでお雑煮を食べた。きのうは天気が悪く寒かったので、きょう温室のイチゴとトマトを収穫した。収穫は孫娘の友菜(高1)と瀬那(小6)。おいしい完熟果実を収穫した。(T)